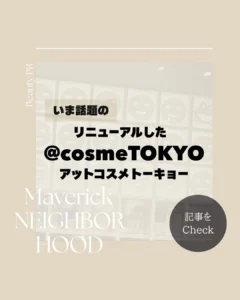化粧品のブランディング事例8選!成功に導くためのコツも解説

ブランディングとは、商品やサービスの価値を高め、ユーザーや社会に独自性を認識してもらうための手法です。
化粧品のロゴやパッケージデザイン、イメージキャラクターなどの視覚的な要素だけでなく、ブランドのミッションや製品のメッセージといった内面的な要素も活用することが重要です。
この記事では、化粧品ブランディングの8つの成功事例や結果を出すためのコツを紹介します。
自社商品のブランディングに取り組みたいとお考えでしたら、ぜひご覧ください。

美容プロモーション・化粧品PRの専門家
マヴェリック編集部
代表 桑原由美子が率いる美容専門のPR会社。1996年の創業からビューティに特化したメディアコミュニケーションを実施。長年のキャリアで築き上げたメディアとの信頼関係を強みとして、WEBを含む美容誌・女性誌へのアプローチを中心に、イベント、インフルエンサーマーケティングなど、常にトレンドや時代のニーズに合わせたPRの戦略と戦術を設計することでブランドや製品の認知度向上に貢献。
化粧品ブランディングが重要な理由
化粧品市場は国内外でブランドが乱立しており、食品や医薬品メーカーなどの他業種も化粧品ブランドを展開し始めていることから、年々競争が激化しています。
そのため、ユーザーに自社の化粧品を購入したいと思ってもらうためにブランディングが必要不可欠です。
「使用するとどんなメリットがあるのか」「どんな人に使って欲しいか」など、確固たるブランドイメージを作り上げましょう。
ブランディングがうまく行かなければ売り上げは伸ばせないので、有名化粧品メーカーの成功事例を参考に力を入れて取り組むことが大切です。
化粧品ブランディングの成功事例8選
有名化粧品メーカーにおけるブランディングの成功事例として、以下の8つを紹介します。
- SK-II(エスケーツー)
- BOTANIST(ボタニスト)
- MEDULA(メデュラ)
- SHIRO(シロ)
- FASIO(ファシオ)
- SKINFOOD(スキンフード)
- BULK HOMME(バルクオム)
- CLINIQUE(クリニーク)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.SK-II(エスケーツー)
SK-IIは1980年に日本で誕生した化粧品ブランドで、ブランドを象徴する独自の天然由来の美容成分「ピテラ」で他社と大きく差別化を図っています。
ピテラには「エイジングサインのケア」「角質のすみずみまでうるおいを与える」「毛穴を目立たなくさせる」などの効果があり、ほかブランドの追随を許さない製品開発力が強みです。
また、桃井かおりさん・綾瀬はるかさん・永野芽郁さんといった有名女優をCMキャラクターとして起用しており、安定感や安心感をアピールしてブランディングしていることが特徴です。
さらに、白地に赤文字という日本国旗を連想させるようなパッケージデザインが目を引き、海外にもファンが多く、国際的な人気の獲得にも成功しています。
北米・香港・シンガポール・中国・ドバイなど世界13カ国で販売されていて、日本発の化粧品ブランドとしてブランディングできていることがわかる事例です。
2.BOTANIST(ボタニスト)
BOTANISTは「答えはきっと自然の中にある。」をコンセプトに、ブランド名の通り自然を意識しているヘア・ボディケアブランドです。
約30万種の植物の中から厳選した植物由来成分や、優しい洗い上がりが魅力的な植物由来の洗浄成分など、強いこだわりが感じられる商品を開発しています。
サスティナビリティや自然に関心があるユーザーをターゲットにしていて、全カテゴリの累計販売個数が1.6億個を突破するほどの功績を残すほど上手にPRできていることがわかります。
また、「本質的でシンプルなライフスタイルや心身の癒しを求め、そこに植物を必要としている」という理念を持っていることから、白背景に黒文字のみと非常にシンプルなロゴデザインを展開。
ブランドの理念と商品のデザインが一致しており、ユーザーに確固たる世界観があることを訴求していて、丁寧にブランディングしていることが伺えるでしょう。
3.MEDULA(メデュラ)
MEDULAは日本初のパーソナライズシャンプーがコンセプトで、3万通りの組み合わせから自分の髪質や理想に合うシャンプーが届くサービスを展開しています。
ブランドメッセージに「私がときめく、私でいよう。」を掲げており、カラフルなボトルカラーや長続きするシャンプーの香りにこだわって製品を開発していることが特徴です。
50万人分の毛髪診断データや12種類のアミノ酸配合など、研究に研究を重ねたシャンプーを開発し、ヘアケアに力を入れたいターゲットにうまく訴求できています。
また、注文した商品に関する情報を美容師から受け取れ、購入後のアフターケアが整っているため、90%以上と高い顧客満足度を獲得。
定期注文では毎回割引価格での販売や継続回数の縛りがないこと、ポイントを貯めて好きな商品と交換できることから、少しでもMEDULAに関心があるユーザーの購買意欲を掻き立てることに成功しています。
4.SHIRO(シロ)
SHIROは北海道産を中心とした自然の恵みを丁寧に、ふんだんに使用している日本生まれの化粧品・生活雑貨ブランドです。
「素材の力を最大限に引き出すこと」「余計なものをできるだけ入れずに作る」といったコンセプトのもと、自然の恵みを余すことなく大切に使い切るという世界観を確立しています。
保湿力のある酒粕や米ぬか、整肌作用を持つジンジャーやゆずなど、どのような自然由来成分が含まれているかを開示しており、優しさや安心感をしっかりとPRしています。
また、2019年にリブランディングしてブランド名を小文字の「shiro」から大文字の「SHIRO」に変更し、誰でも使いやすいようにイメージを刷新。
性別に関係なく自然の恵みを存分に味わえる製品開発に務めており、老若男女を問わずに愛されるブランドに進化しました。
「自然に関心があるターゲットに手に取ってもらいたい」という思いが伝わるブランディングだとわかります。
5.FASIO(ファシオ)
FASIOはコーセーが展開するプチプラコスメブランドで、ブランド名はラテン語で「成し遂げる」という意味です。
以前はしっかりめの華やかメイクを売りとしていましたが、2021年5月のリブランディングにあたって新しいブランドコンセプトとして「なじむ、らしさ、つづく。」を掲げます。
20代女性をターゲットとして、自分らしさや等身大の美しさを追求するために、肌へのなじみやすさを追求。
くすんだブルーや淡い色合いのピンクなどのニュアンスカラーをパッケージデザインに採用し、ゆったり感や柔らかさのあるイメージに仕上げ、売上回復に成功します。
さらに「ヒトヌリルージュ」や「まつ毛 ハリコシアップ美容液」など、どのような性能を持つ化粧品かが一目でわかるネーミングを採用しています。
洗練されていてユーザーのニーズに合う化粧品を開発していることがわかり、ユーザーファーストのブランドであることが明確に訴求できていることがポイントです。
6.SKINFOOD(スキンフード)
SKINFOODは「食べてカラダにいいFOODをお肌にも」という理念のもと、食べ物から生まれた化粧品を展開している韓国発の化粧品ブランドです。
研究者が実際にフルーツや野菜などをつぶして自分の肌に塗り、安全性を確かめてから商品を開発しているほど、安心・安全を前面に売り出したブランディングに努めています。
韓国の清酒やブラジル産の黒糖などユーザーに馴染みのある食べ物を採用し、一部オーガニックの素材を使った商品を販売しているので、自然派のユーザーから関心を集めています。
また、直営店舗では実際に製品を使用できたり、サンプル品が配布されたりしているので、製品の品質を自分の肌で確かめてから購入できるのも魅力。
安全性を強く訴求していて自社の化粧品の品質に自信があるからこそなし得るサービスであり、ファンをしっかりと獲得しています。
7.BULK HOMME(バルクオム)
BULK HOMMEは「世界のメンズビューティをアップデートすること」をヴィジョンに掲げる日本生まれの男性向け化粧品ブランドです。
日本では「スキンケアは女性がするもの」というイメージが根強いなか、「スキンケアは特別なことではなく、男性にとっても欠かせないもの」と押し出し、男性ユーザーから興味を引くようにブランディングしています。
たとえば、BULK HOMMEの製品のほとんどは白地に黒文字のみというシンプルなパッケージデザインで、男性が気軽に購入しやすいように工夫されています。
また、「どんな化粧品を選べばいいかわからない」「店頭で購入するのは恥ずかしい」といった男性でも買い求めやすいように、定期コースを展開していることも特徴です。
「シャンプー×トリートメント」「洗顔料×化粧水」など、最初からセットになった商品が自宅に届くので、スキンケアに取り組んだことがない男性にもアピールできています。
8.CLINIQUE(クリニーク)
CLINIQUEは世界で初めて皮膚科学の見地から研究・開発された、アメリカ・ニューヨーク生まれのスキンケアブランドです。
ブランド誕生から約50年間で約600万回にわたるアレルギーテストを実施しており、化粧品は100%無香料かつ低刺激と肌への優しさを追求した商品が特徴です。
CLINIQUEの全ての化粧品は、皮膚科医の監修のもとで臨床アレルギーテストを行ない、厳格な基準をパスしてから販売されるので、安心感を強く訴求できている点もポイント。
また、日本国内で販売されているCLINIQUEの製品は、国に許可された成分を日本人の好みなどを考慮して使用しています。
販売する国での人々の匂い・色・感触などの好みを踏まえたうえで化粧品を開発しており、製品に対する強いこだわりや世界観を大切にしていることがわかります。
化粧品ブランディングで結果を出すためのコツ
化粧品のブランディングに成功し、売り上げを伸ばすために押さえておきたいコツは以下のとおりです。
- ターゲットを具体的に設定する
- ブランドコンセプトを明確にする
- 全ての媒体で世界観を統一する
それぞれ詳しく解説します。
ターゲットを具体的に設定する
「会社員の25歳の女性」「35歳で子育て中のママさん」など、化粧品のターゲットを具体的に設定します。
ターゲットが明確であれば今後のブランディングの方向性が決まるので、最初にできるだけ細かく決めるのが大切です。
年齢や性別はもちろん、職業や収入などの経済状況、最終学歴や生活スタイル、好きなことや休日の過ごし方など、可能な限り細かく設定するほどターゲットが明確になります。
また、ターゲットが決まったら訴求文やデザインなども決まるため、ブランディングと同時にマーケティングもしやすくなるでしょう。
ブランドコンセプトを明確にする
「高級志向でかっこいい」「無添加で肌に優しい」など、化粧品のブランドコンセプトを明確にすることも重要です。
コンセプトがあいまいだと、どのような人に向けて発売しているかわからず、ターゲットに注目してもらいづらいです。
ユーザーに向かってどのような魅力や価値を提供しているのか、ブランドとしての指針やイメージをはっきりと示すためにブランドコンセプトを明確にしましょう。
ユーザーに「あなたのために化粧品を作りました」という思いが伝わるように、確固たるコンセプトを打ち出してください。
全ての媒体で世界観を統一する
「ホームページではかわいい印象なのに、SNSではクールでかっこいい雰囲気に仕上げられている」というような媒体ごとに世界観が異なっているとユーザーは化粧品に対して明確な印象が持てません。
どのような人に対して化粧品を発売しているかがわからないので、どれだけたくさんアピールしても購入まで至らない可能性があります。
ちぐはぐな印象にならないように、全てのメディアで世界観を統一して、設定したターゲットにアピールすることが重要です。
化粧品ブランディングにお悩みの方はマヴェリックまで
化粧品は競合他社や類似商品が多いので、売り上げを伸ばすためにはブランディングが大切です。
CLINIQUEやSK-IIなど有名メーカーの事例を参考に、自社の化粧品のブランディングに積極的に取り組んでみましょう。
そうはっいても、「ブランディングはどこから手をつけたらいいかわからない」「ブランディングに取り組んでいるけど成果が出ない…」とお悩みの化粧品ブランドの担当者は少なくないのではないでしょうか。
マヴェリックでは、これまで数多くの化粧品のブランディングをサポートして参りました。
化粧品のブランディングにお困りでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。